毎年GW明け頃に流行すると言われている溶連菌はどんな病気なのでしょうか?
子どもに多い病気ですが感染経路や症状・治療方法など気になりますよね。
我が家の息子さんも8歳の頃に溶連菌にかかりました。
溶連菌の感染経路や症状、子どもの場合の治療方法についてまとめています。
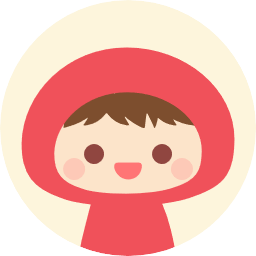
たらこっこ@nikonikotarakoです。
溶連菌はうつる病気なので注意が必要です
目次
溶連菌の感染経路や症状は?

溶連菌感染症は溶血性連鎖球菌という細菌に感染して起こる感染症です。
どんな症状が出る?
- 発熱
- のどの痛み
- 発疹
- イチゴ舌(イチゴのように舌が赤くブツブツ腫れる)
- 倦怠感
- 嘔吐が出る場合もある
子どもはかかりやすい?
学童期の子どもに多い感染症と言われています。
3歳以下や大人では症状が出にくいようですが、かかってしまう場合もあるので注意が必要です。
風邪とは違うの?
発疹やイチゴ舌などの症状が必ず出るわけではなく、発熱やのどの痛みだけの場合もあります。
そのため一般的な風邪と見分けがつかないこともあります。
風邪との大きな違いは鼻水や咳が出にくいという点です。
のどが痛くて風邪のような症状だけど鼻水や咳は出ていないという場合には、溶連菌感染症を疑ったほうが良いかもしれません。
感染経路は?
溶連菌感染症の感染経路は接触感染と飛沫感染です。
最も感染力が強いのは症状が出始めた頃です。
きょうだい同士での感染は50%程度というデータもあります。
保育園、幼稚園、小学校などの集団生活の場でも感染しやすくなります。
川崎病は新型コロナウイルスとも関連しているというニュースもありました。
息子もかかりましたがとても怖い病気です。
溶連菌感染症の診断方法は?

迅速診断
病院を受診して溶連菌感染症が疑われる場合には迅速診断という方法で検査をする事があります。
綿棒で喉をこすって溶連菌が含まれているかどうかを確認する検査です。
15分程度で検査結果が出ます。
正確性は80~90%ほどです。

ボクもこの方法で検査をされたよ。
喉の奥をグリグリっとされて、ちょっとだけオエッとなるけどすぐに終わったよ
それ以外の診断方法は?
場合によっては『培養検査』や『血液検査』などで診断することもあります。
病院の指示に従って適切な検査をしてもらいましょう。
溶連菌の治療方法は?

溶連菌の治療は抗生物質の服用です。
抗生物質は10日前後は確実に服用する必要があります。
症状が良くなったからといって、途中で服用をやめる事は絶対にやめましょう。
途中で服用をやめてしまうと、再発をしたり、合併症にかかるリスクを高めることになります。
処方された薬は必ず飲みきるようにしましょう。
いつから登園・登校できる?
溶連菌感染症の場合には明確な出席停止期間はありません。
- 医師が感染のおそれが無いと認めた場合
- 抗生薬服用後24時間経過後は感染力は無くなる為、それ以降は登校可能
このような判断がされる場合が多いようです。
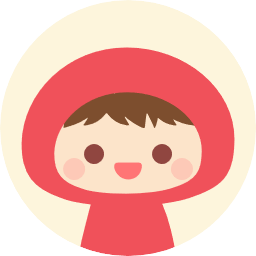
子どもは色々な病気にかかる可能性があります。
ただの風邪なのか、他の病気なのか判断に迷う事も多いですよね。
そんな時に役立つホームケアの本は1冊用意しておくと安心ですよ!
長引いた溶連菌治療の体験談

1日目:休日に37.5度の発熱と下痢
⇒ 休日診療所を受診
⇒ 抗生剤と整腸剤が1日分処方される
2日目:熱は36.5度。のどの痛み
⇒ 小児科受診で溶連菌感染症と診断される
⇒ 抗生剤を3日分処方される
⇒ 登校は様子をみて明日から可能と言われる
⇒ 3日後に受診するように言われる
3日目:のどの痛みが無いので登校する
5日目:3日経過したので再び小児科受診
⇒ 抗生剤を10日分処方される
⇒ 2週間後に尿検査のため受診するように言われる
2週間後:尿検査
⇒ 朝の尿を採取して午後に受診。問題なし。2週間後にもう一度検査をする
さらに2週間後:尿検査
⇒ 前回と同様に朝の尿を採取して午後に受診。問題なし
最初の発熱で休日診療所を受診したのが6月14日で最後の尿検査をしたのが7月23日でした。

熱やのどの症状はすぐに治ったのに、こんなに長い期間小児科通いをすることになるとは思わなかった…
息子の場合、転勤や引っ越しで今まで多くの小児科にかかってきました。
いくつか行った小児科の中でも、この時の病院はとても時間をかけて丁寧に診察する小児科という印象でした。
病院によって治療方法は異なると思いますが10日以上の抗生物質の服用というのは驚きました。
症状が回復すると薬の服用を忘れがちです。
お子さんに抗生物質を飲ませ続けるのもなかなか大変です。
でも途中で服用をやめてしまう事だけは絶対にやめましょう。
医師の指示に従って最後まできちんと治療をすることが大切です。
まとめ
溶連菌の感染経路や症状について体験談をまじえてまとめました。
多くの場合は息子のようにそれほど強い症状が出ずに回復する事が多いようです。
風邪とは違う溶連菌感染症というものがあると頭に入れておけば、いざという時に安心かもしれませんね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
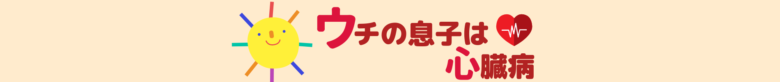
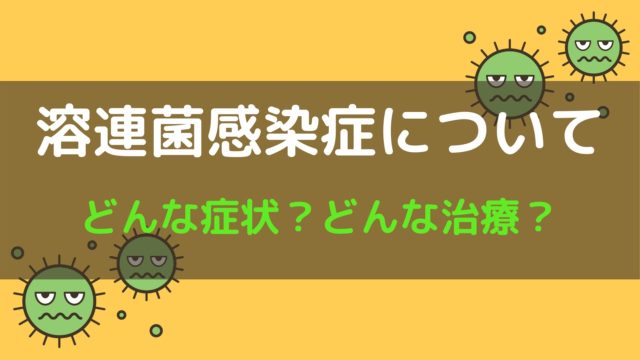
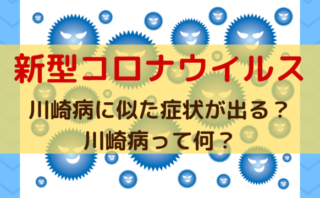
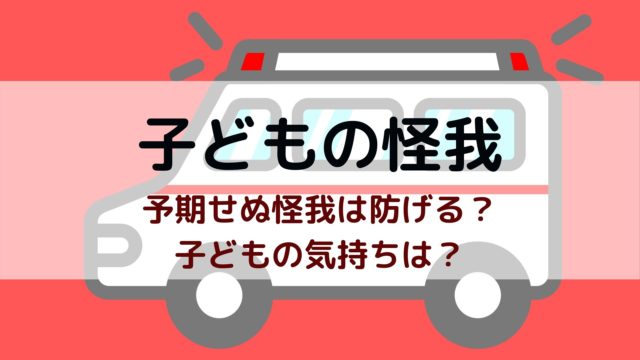
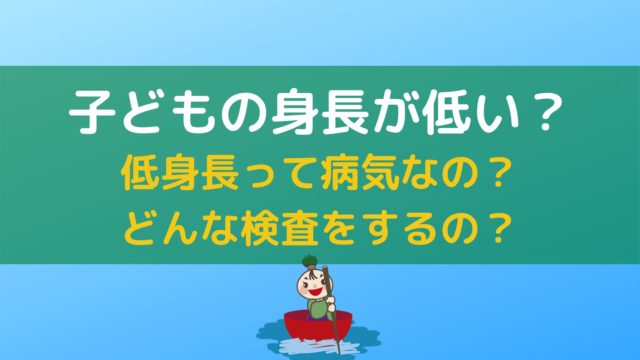

コメント