こんにちは、たらこっこです。
もしも子どもが入院する事になったら子どもへの治療の説明はどうすれば良いのでしょうか?
何歳頃からどの程度の説明が必要なのでしょうか?
心臓病をはじめ今までいくつかの疾患で入院してきた息子の体験をもとに子どもへの治療の説明方法についてまとめています。
目次
治療を受ける子どもへの説明は必要なの?

息子の場合、今まで3つの病院での入院経験があります。
どの病院でも共通していたのは、入院の際にこのように聞かれることです。
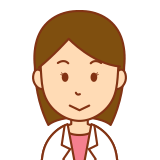
ご本人への説明はできていますか?
ご本人はどの程度理解していますか?
子どもが入院する時には、子どもの年齢に応じて理解できる程度にきちんと説明しておく必要があるという事です。
病院によっては紙芝居や人形を使って、子どもにこれから受ける治療や手術の説明をしてくれます。
子どもに説明をする理由は?
- 病気についてきちんと子どもに説明する事で子ども自身が『がんばって治そう』という気持ちになります。
子ども自身が治療に積極的になれば、医師や看護師さんの治療を怖がらずに受け入れる事ができます。
- 子どもに何の説明もしないと、不必要に悪い想像を膨らませる事があります。理解できる程度の説明をしてあげることで、安心して治療を受ける事ができます。
子どもが理解できるのは何歳頃から?
2歳頃まで
- 病気への理解はほとんどできない
- 親と離れる事への不安はとても強い時期
- 注射や検査などの痛い処置は敏感に察する事ができる
- 泣いたり嫌がったりする事が多い年齢
3歳頃から
- 病気についてなんとなく理解することができる
- 絵本などを使って注射や検査などの説明を理解することができる
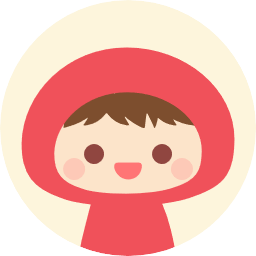
幼稚園や保育園に通う頃になるとだいぶ理解できるようになります。
まだ難しい事が理解できない年齢でも、親の言った事がわかる年齢であれば子どもにわかるように簡単な説明をしてあげる事が大切です
子どもへの説明はどのようにすれば良い?
- 入院や治療は悪いところを治すために必要な事だとわかりやすく伝える
- 子どもに質問を投げかけながら子どもが知りたい事にはきちんと答える
- できる限り子どもに嘘はつかずに説明する
- 病気になった事は誰のせいでもないという事を伝える
子どもの入院の年代別ポイントは?
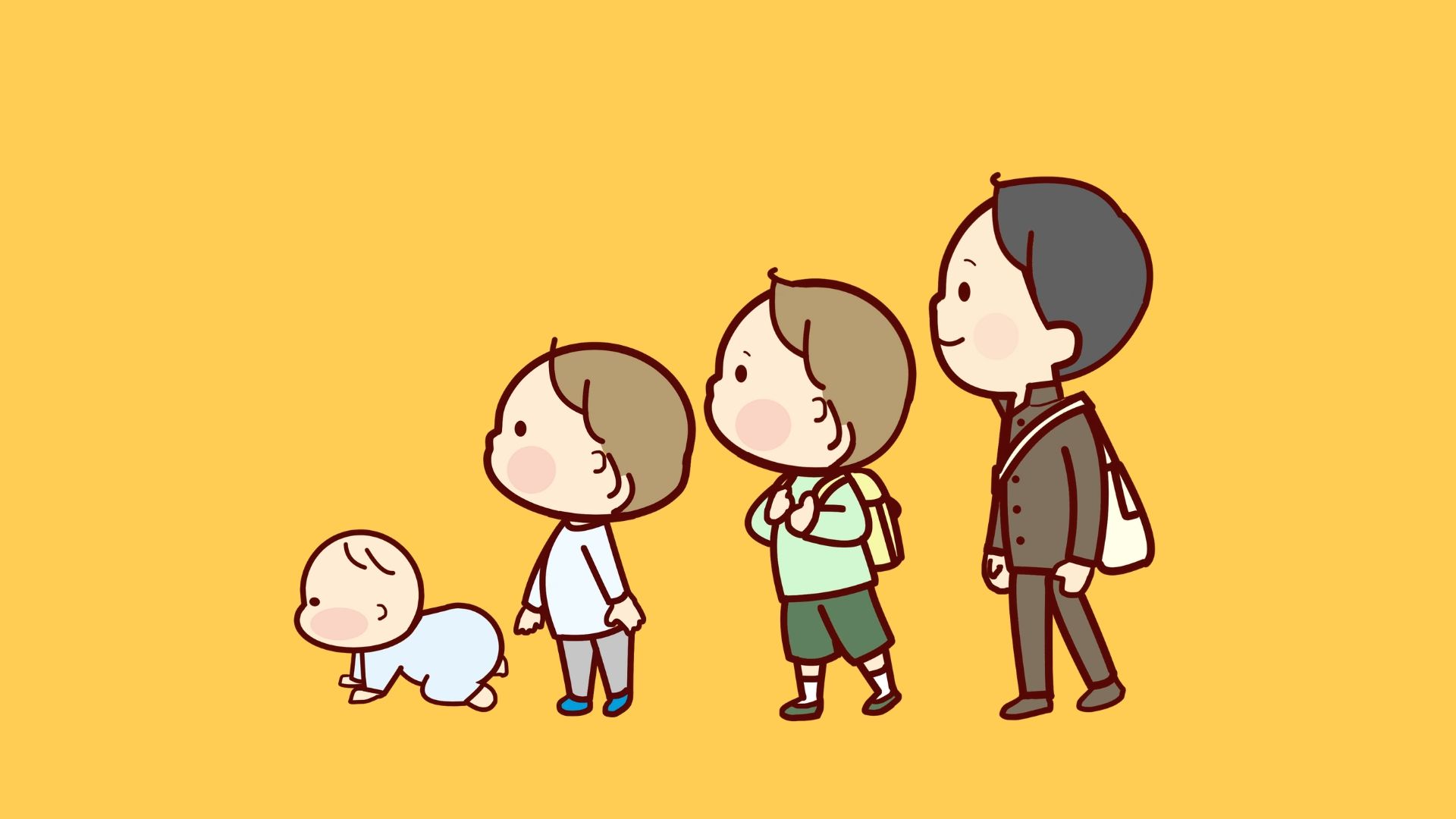
子どもの年代によって、病気の説明の方法や入院生活は変わってきます。
病院によって違いがあると思いますが、実行できるポイントだけでもやってみるといいですよ。
0歳~12か月
- 親しみのある物で安心する事ができる
- お気に入りのおしゃぶり、おもちゃ、タオルなどを持参すると良い
- 普段使い慣れているコップや哺乳瓶を持参すると良い
1歳~3歳
- 入院に持っていくパジャマやタオル等を子どもに選ばせながら一緒に準備すると良い
- おもちゃもお気に入りの物を1個か2個選ばせる
- 医師や看護師さんが何か治療行為をする時には、横でお母さんも一緒に「ちょっとここを押さえるよ」等と声をかけると良い
- 入院中にお母さんがその場を離れる時には「ちょっと売店に行ってくるね」「外で待ってるからね」と状況を伝えるようにすると良い
3歳~5歳
- 病院でどんな治療をするのか、わかりやすく説明しておく
- 病院ごっこでぬいぐるみに包帯を巻いたりして、実際に行う事を事前にやってみる事も効果的
治療をさせたいあまりに『泣いてるとお母さん帰るよ!』などと子どもをおどすような事を言うのは逆効果です
小学生
- 入院や治療の必要がわかった段階で説明をするようにする
- 病気や手術について、子どもがわかる範囲でできる限りきちんと説明をする
- 子どもからの質問には丁寧に答える
- 子どもの質問にどう答えたら良いのかわからない場合には「次に病院に行った時に先生に聞いてみよう」と言って病院に相談する
中学生以降
- 入院や治療の必要がわかった段階で話し合いの場を作り子どもの不安や疑問を聞く
- 自分自身で何をしたいか決定できる年齢なのでそれを見守りサポートするようにする
- 子ども自身が医師や看護師さんに質問できるようにすると良い
乳幼児への説明に役立つ本
乳幼児への説明の時には本やDVDを使うのもわかりやすくていいですね。
病気に関する本は別記事でまとめていますので参考にしてみてください。
入院治療の説明-息子の場合
鼠径ヘルニアと臍ヘルニアの手術入院(4歳)
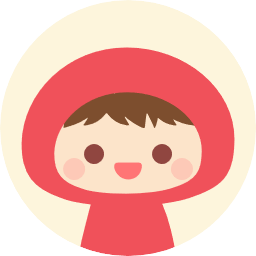
すごくデベソになってるでしょ。
だからここを治してもらうんだよ。
手術するけど眠ってる間に終わるんだよ

デベソ~
デベソ~
『デベソ』という言葉にハマったのか入院を嫌がる事はありませんでした。
川崎病で緊急入院(4歳4ヵ月)
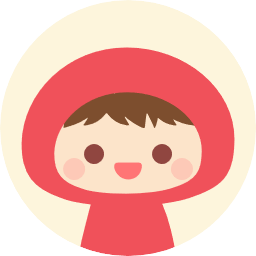
体に悪いバイキンがあるんだって。
すぐに入院だからおうちには帰れないよ

えー?入院?
何階のどの部屋かなぁ?
入院が割と好きな息子は緊急入院を喜んでいました。
緊急入院だったので最初に点滴を刺される時だけ大泣きでしたが、その後は暇を持て余す入院生活でした。
低身長の検査入院(8歳)
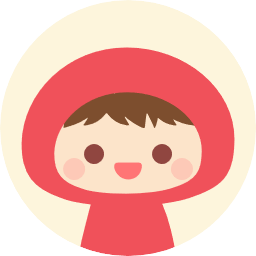
身長がちゃんと伸びるかどうか検査しなくちゃいけないんだよ。
点滴をするだけだよ

新しい病院で入院するの楽しみだな~
検査入院で元気な状態での入院だったので、検査前の空腹に耐えるのが辛かったです。
子どもの気持ちがわかる本
入院となると親も子どもも平常心でいられないのは当たり前の事です。
親自身も準備する事が多くて気持ちも落ち着かないため、子どもに対していつも以上に怒りっぽくなってしまうなんて事もあると思います。
でも一番不安なのは子ども自身です。
子どもが何を考えているのか普段から理解することが大切かもしれません。
世界的なベストセラーの育児書。16か国以上で翻訳されています。子どもの言い分や科学的な裏付けなどを分析。ママやパパがどのように対応するべきなのかという方法が書かれています。子どもが泣くのは理由がある。こんな事を考えていたんだとわかる画期的な育児書です
- 子どもに対して怒らない日はない毎日でしたが、この本を読んで子どもに対する怒りをグッとおさえられるようになりました
- 毎日のように起こる子どもの困った言動がなんとなく理解できるようになりました
- 子どもの年齢ごとの対処法が書かれているのでわかりやすかったです
- 絵がわかりやすくて忙しい育児の合間の流し読みでも理解できました
- 子どもと関わる仕事なので読みました。自分が育児をしていた時に出会いたかった本です
まとめ
以前カテーテル検査入院をした時に、向かいのベッドに2歳位の女の子がいました。
まだおしゃべりができないようですが、お母さんの言っている事は理解できています。
お母さんは何をするにも「ママ〇〇してくるね」と説明していました。
注射の前にも「ここにチクンしないといけないんだって」と説明していました。
泣いて嫌がる子どもに根気よく説明していました。
カーテン越しにその様子を感じて、私もあの頃はこうだったのかな…と思いながら13歳の息子の付き添い入院をしていました。
入院は子どもにとって大きな不安と恐怖がともなうものです。
治療をしてくれるのは医師や看護師さんですが、子どもの心を一番理解できるのは、お母さんやご家族だと思います。
我が子の心を理解して、きちんと説明をして寄り添う事が大切ではないでしょうか。
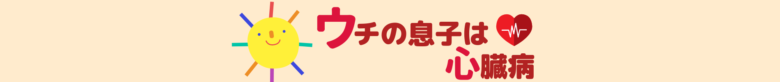
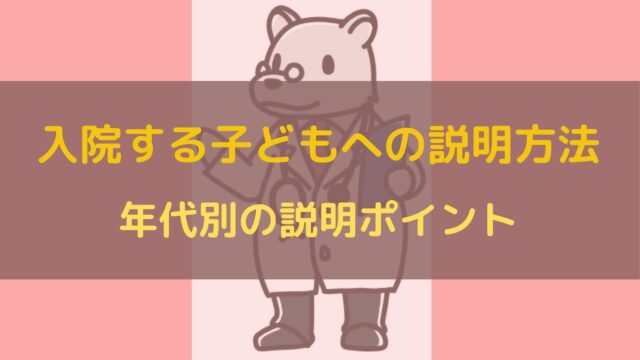
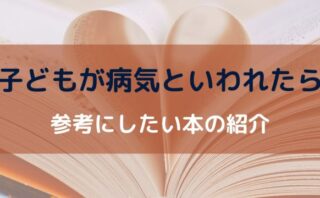


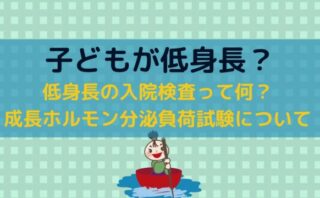
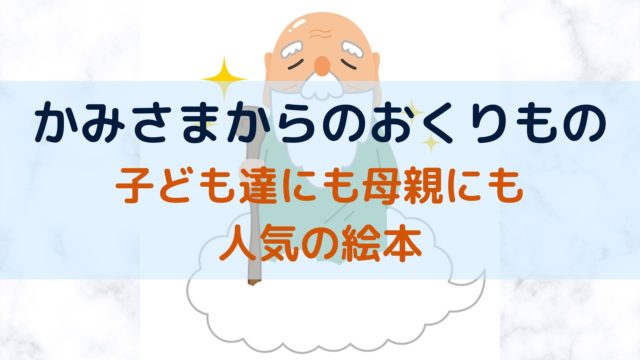
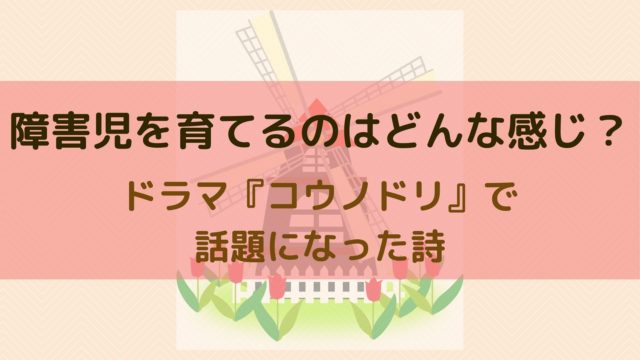

コメント